
光と分子
*この解説は、濵口宏夫「光と分子」、化学のすすめ(筑摩書房)をホームページ向けに改変したものです。
光はこの世界の成り立ちそのものと深く関わる極めて重要な役割を果たしている。例えば、光を抜きにして生命を語ることはできない。生命活動を支えるエネルギーは、つきつめて考えると、すべて太陽から供給される光エネルギーである。また、生体はさまざまな光情報処理機能を備えていて、それに基づいて外界の環境変化に対応している。視覚がその代表例である。このような重要な役割はしかし、光によって単独で演じられている訳ではない。そこには必ず光の共演者である分子が介在し、光と分子の二人三脚によって初めて様々な機能が発現するのである。
光はまた分子の世界へのガイドとしても独自の役割を果たす。分子の世界は極微の世界であり、どんな顕微鏡を用いても動きまわる分子の姿を直接に見ることはできない。しかし、分子が光に託してわれわれに発信してくるスペクトルというメッセージを解読することにより、間接的にではあるが分子の姿を捉えることができる。しかも1ピコ秒(1兆分の1秒)という超高速の分子の動きも観察することができる。
この章では、まず光と分子がその本質においてどのように関わり合っているのかを、いくつかの思考実験を交えて説明する。つぎに、光によって分子構造やその変化を調べる分子分光学の原理を解説する。最後に、光合成の初期過程である光電子移動反応や、視覚の初期過程である光異性化反応など、光と分子の演ずる興味深い化学現象を、分子分光学によって解明しようとする最先端の研究例について述べ、現代化学のエキサイティングな一断面を紹介する。
1 光とは何だろう
光は電子のエネルギーのもと
太陽電池は光を電流に変える。電流は電子の流れである。では太陽電池に光を当てると何故電流が流れるのだろうか。太陽電池の材料であるシリコンの中にある電子が、光を吸収してエネルギーの高い状態に移り、その結果動きが活発になるからである。一般に、エネルギーの高い状態にある電子は動きが活発で、他に対して仕事をすることができる。このような状態を励起状態という。一方、エネルギーが低く、他にたいして仕事ができない状態を基底状態という。基底状態にある電子は、光を吸収して励起状態に移る(遷移する)ことができる。つまり光は電子のエネルギーのもとであり、光を吸ってエネルギーを貰った電子は、元気な励起状態となり、活発に動きまわって仕事をすることができるようになるのである。逆に励起状態の電子はそのエネルギーを光として放出し、基底状態へと遷移することができる(図1)。
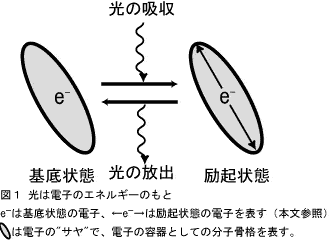
図1
共鳴エネルギー移動
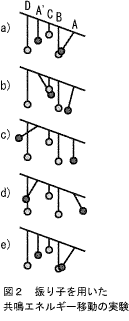 次のような実験をしてみよう(図2)。タコ糸の両端を固定し、数個の振り子をぶらさげる。空気の抵抗が無視できる場合には、振り子の振動数は糸の長さで決まる。数個の振り子のうち、AとA'
の2つだけが糸の長さが等しいとする。Aを金槌などで軽くたたいて、振り子をタコ糸と直角方向へ振動させる(図2(a))。しばらく観察すると、Aの振幅が小さくなるとともに、A'だけが少しずつ動き始め(b)、ついにはAが静止しA'のみが振動するようになる(c)。さらに時間が経過すると、A'の振幅は小さくなりAだけが再び動きはじめ(d)、A'が静止しAだけが振動する最初の状態に戻る(e)。一方AとA'以外の振り子はすべて終始静止したままである。すなわち、金槌から最初振り子Aに与えられたエネルギーは、AとA'の間だけを行き来する。同じ振動数の振動子(振り子を一般化した概念)間でエネルギーのやりとりが起こることを共鳴エネルギー移動と呼ぶ。複数の音叉のうち一本を鳴らすと、同じ音の音叉のみが鳴り出すのも共鳴エネルギー移動によるものである。
次のような実験をしてみよう(図2)。タコ糸の両端を固定し、数個の振り子をぶらさげる。空気の抵抗が無視できる場合には、振り子の振動数は糸の長さで決まる。数個の振り子のうち、AとA'
の2つだけが糸の長さが等しいとする。Aを金槌などで軽くたたいて、振り子をタコ糸と直角方向へ振動させる(図2(a))。しばらく観察すると、Aの振幅が小さくなるとともに、A'だけが少しずつ動き始め(b)、ついにはAが静止しA'のみが振動するようになる(c)。さらに時間が経過すると、A'の振幅は小さくなりAだけが再び動きはじめ(d)、A'が静止しAだけが振動する最初の状態に戻る(e)。一方AとA'以外の振り子はすべて終始静止したままである。すなわち、金槌から最初振り子Aに与えられたエネルギーは、AとA'の間だけを行き来する。同じ振動数の振動子(振り子を一般化した概念)間でエネルギーのやりとりが起こることを共鳴エネルギー移動と呼ぶ。複数の音叉のうち一本を鳴らすと、同じ音の音叉のみが鳴り出すのも共鳴エネルギー移動によるものである。
共鳴エネルギー移動がおこる仕組みを、次のように3段階に分けて考えることができる。1) まず振り子Aがタコ糸を一定の振動数で揺さぶる。その結果、タコ糸が同じ振動数で周期的に振動して、タコ糸上に波動が生ずる。2) 生じた波動は、タコ糸上を伝わっていき、ぶらさがっている全ての振り子をAと同じ振動数で周期的に揺さぶる。3) 揺さぶられた振り子の振動数がタコ糸上の波動の振動数と一致すると、共鳴が起こりその振り子(A')が揺れはじめる。これはブランコをこぐとき、ブランコのゆれの振動数に合わせて体を前後に揺さぶっていると、だんだん大きく振れてくるのと同じ原理である。
電子間の共鳴エネルギー移動と電磁波
分子中の励起状態の電子は、振り子と同様に振動していて、一種の振動子とみなすことができる。その振動数は分子の種類によって決まる一定の値を持つ。同一種の分子AとA'があり、ある時刻において分子A中の電子が励起状態にあり、分子A'中の電子が基底状態にあったとしよう。振り子のモデルで考えると、A中の電子は大きく振動している振り子であり、A'中の電子は静止した振り子である。時間が経過すると、振り子のモデルの時と同様に、電子間に共鳴エネルギー移動がおこる。分子A中の電子はエネルギーを放出して励起状態から基底状態に遷移し、A'中の電子がこのエネルギーを受け取って基底状態から励起状態へと遷移する。さらに時間の経過するにつれ、エネルギーはAとA'の間を往復する。
電子間の共鳴エネルギー移動も、振り子のモデルの時と同様、3段階に分けて考えることができる。1) 分子A中にある励起状態の電子が周囲の電磁場注)を揺さぶり、電磁波を発生する。2) 電磁波が真空中を伝わって行き、分子A'中の電子を揺さぶる。3) A'中の電子が電磁波のエネルギーを吸収し励起状態へ遷移する(図3)。振り子のモデルとの対応を考えると、電磁場は振り子を吊っているタコ糸に、電磁波はタコ糸上を伝わる波動に相当する。
注) 電磁場とは、電場と磁場の総称である。電場中の電荷は電場の大きさと方向に応じた電気力をうける。磁場中の磁石は磁場の大きさと方向に応じた磁気力をうける。このように、電磁場は、電荷と電荷の間に働く電気力や、磁石と磁石の間に働く磁気力をより一般的に表すのに用いられる電磁気学の基礎概念である。物質が全く存在しない真空でも、電磁場は存在する。電磁場の波動である電磁波は、したがって、真空中を伝わることができる。
電子間の共鳴エネルギー移動のしくみから、電磁波が「電子のエネルギーのもと」という意味で、光と同じ本質を持っていることがわかった。そこで光は電磁波であると考えて先に進むことにしよう。
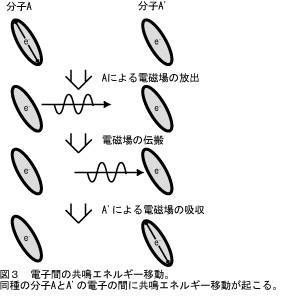
図3
光の波動性
光は電磁波として波動の性質を持つ。電磁波の振動数ν は、ある空間の一点で電磁場が1秒間に何回振動するかを表す数であり、その単位はHz=s-1である。振り子のモデルから容易にわかるように、ν は電磁波を放出する励起状態の電子の振動数に等しい。電磁波の波長λ は、電子が1回振動したとき電磁波が進行する距離である。したがって電磁波は1秒間にνλ の距離を進行することになるが、これは真空中の光速度cに等しいはずである。このことから次の関係が成立することがわかる。
ν =c/λ (1)
振動数と波長は光の波動性を特徴づける基本的な量で、以後頻繁に出てくる。場合によっては、振動数ν の代わりに波数ν˜ を用いることがある。
ν˜ =1/λ =ν /c (2)
この関係式からわかるように、波数は1cmに波が何個あるかを表す量であり、その単位はcm-1である。
電磁波にはその波長によって多くの異なる名前がある。すでに第I章で出てきたように、電波も電磁波の一種である。東京近辺では、NHKのラジオ放送に用いられている電波の波長は500m、振動数は6×105Hzである。一方、青緑色の光は500nm(1nm=10-9m)、振動数は6×1014Hzである。波長や振動数が9桁も違っていても、電波と光は本質的に同じものである。電波を出しているNHKの放送局のアンテナの中にはたくさんの電子があって、それらが一斉に6×105Hzの振動数で振動している。そうすると、同じ振動数の電磁波(電波)が放出され、空間を伝わってラジオ受信器に到達する。ラジオ受信器の中にはコイルとコンデンサーからなる同調回路があって、電子が6×105Hzの振動数で振動しやすくなっている。その結果、共鳴エネルギー移動によりコイルの導線中の電子が移動し、6×105Hzの電子信号を発生する。この高周波信号を検波(高周波信号に重なった低周波信号を取り出すこと)して音声信号を取り出すことにより、ラジオの音声が聞こえるようになるのである。このラジオ放送の仕組みは、分子中の電子が光を放出したり、吸収したりする仕組みと同じである。唯一の違いは、ラジオ局のアンテナの長さがmのオーダーであるのに対して、分子の大きさがnmのオーダーであるということである。この違いに対応して、振動数も大きく(上の例では9桁)違ってくるのである。分子は超ミクロ世界の光のアンテナであると考えることができるのである。
狭い意味での「光」は可視光を意味する。可視光の波長はおおよそ400nm(紫)から700nm(赤)の範囲にある。広い意味での「光」は、可視光に加えて赤外光と紫外光を含む。赤外光はさらに近赤外光(波長700nmから2.5μm)、赤外光(波長2.5μmから25μm、波数4000cm-1から400cm-1)、遠赤外光(波長25μmから1mm、波数400cm-1から10cm-1)に分けられる。ただし、これらの名称や区分は慣習的なものであって、その境界となる波長は単なる目安であることを注意しておく必要がある。本章では以下、「光」を赤外光と紫外光を含めた広い意味で使う。
光の波動としての重要な性質に以下に述べる偏りがある。偏った光を偏光という。振り子のモデルでは、タコ糸上に発生する波の揺れる方向は、進行方向に垂直である。同様に電磁波における電磁場の振動の方向は、進行方向と垂直である。このような波を横波という。いま電磁波の進行方向をz方向としよう。そうすると、電磁場(偏光を議論するときには電場を考えるのが普通である)の振動方向としてx方向とy方向の2つの可能性がある。z方向に進行し、電場がx方向に振動する偏光をx偏光、電場がy方向に振動する偏光をy偏光という。このように電場がある特定の方向にのみ振動する偏光を直線偏光という。これに対して、電場の振動方向が時間とともにxy平面内で回転する偏光を円偏光という。円偏光には右回りのものと左回りのものがある。第VII章でとりあげられる光学活性の議論では、円偏光が重要な役割を果たす。偏っていない通常の光の議論では、x偏光とy偏光が等しい割合で足し合わされたものである。光を使って分子の性質を調べようとするとき、偏光は大変役にたつ。
光の粒子性
光は粒子としての性質も示す。以下のような思考実験をしてみよう(図4)。光源とそこから放射される光の強度を測定する検出器を用意する。光の強度は検出器に接続されたメーター(0から10まで1きざみで目盛ってあるものとする)で読み取れる。まず光源から出る光の強度を調節してメーターの読みがちょうど10となるように調節する(図4(a))。次に、光の強度を1/10に減らすフィルターを検出器の前に置くと、メーターの針は1を指すはずである(b)。スイッチを切り換えてアンプの倍率を10倍にするとメーターの針は再び10を指す(c)。さらにフィルターを1枚追加して光の強度を1/10にし、同時にメーターのスケールを10倍にする(e)。このような実験を3回、4回と繰り返して行くと何がおきるだろうか。最初の数回の間はメーターの針は必ず10を指す。しかし、10回、15回と繰り返して光の強度を弱くしていくと、奇妙な現象が起き始める。さらに光の強度を弱くしていくと、メーターの針はほとんどの時間ゼロを指し、ごくたまにピコンと振れるだけとなる。つまり光の強度を極端に低くしていくと、光が検出器に到達した時のみメーターが振れるような状況がつくりだされるのである。このことから、光は1個、2個と個数を数えることができる粒子としての性質を持った、エネルギーのかたまりであると考えることができる。粒子としての光は、光子あるいはフォトンと呼ばれる。一個の光子が持つエネルギーを光子エネルギーという。
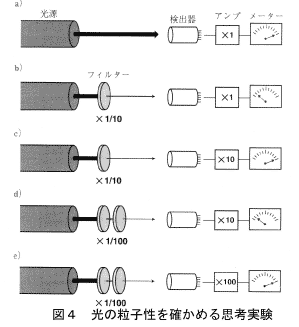
図4
光の二重性とプランク定数
光は波動(電磁波)としての性質と粒子(光子)としての性質を併せ持つ。この光の二重性の問題は、多くの初学者の頭を悩ませる難題である。たしかに、「海の波」のような波動の概念と、「パチンコ玉」のような粒子の概念は両立しない。しかし、電磁波や光子はこのような通常の意味での波動や粒子なのではなく、より抽象化された「波動」や「粒子」なのである。例えば抽象化された「波動」である電磁波は真空中でも伝わることができるし、また抽象化された「粒子」である光子の質量はゼロなのである。
光の二重性を最も端的に表すのは、波動としての性質を表す量である振動数ν と、粒子としての性質を表す量である光子エネルギーEが、極めて簡単な関係式(3)で結び付けられているという事実である。
E=hν (3)
ここでhはプランクの定数である。この関係式が成立することは様々な実験から検証されており、疑いの余地のないものである。しかしそれが何故成立するのかを量子論の枠組みの中で説明をすることはできない注)。量子論には、式(3)と同様、実証することはできても説明することができないいくつかの基本式があり、それらはいずれもプランク定数を含んでいる。プランク定数のこの不思議な特性は、量子論の根幹とかかわるものであり、これらの基本式をいかに容認する(説明を求めてはならない)かが、量子論を習得するうえで重要な鍵となる。光、電子、原子、分子に関する膨大な実験結果が、量子論によりすべて見事に説明されてしまうという事実を学ぶと、これらの基本式が当然のこととして受け入れられるようになる。
注) 将来、量子論の枠組みを超えた新しい理論が登場して、(3)式の説明を与える可能性は否定できない。
光の波動性は光が強いときより顕著に現れる。通常、我々が明るいと感じる時の光の強度はすでに十分大きく、干渉や回折など光の波動としての性質が観測されやすい状態にある。一方、光の粒子性は光の強度が極めて小さい時にのみ顕在化するので、我々が光の粒子性を日常実感することはない。1で、電子間の共鳴エネルギー移動を、振り子のモデルと関連させて議論した。このときには、便宜上、一個の電子が電磁波を放出したり吸収したりすると考えた。厳密に言うと振り子のモデルとの対応は、1個の電子ではなく、十分に大きな数の電子の集合について考えたときのみ成立する。個々の電子について考えるときは、1個の励起状態の電子が1個の光子を放出して基底状態に遷移し、他の1個の基底状態の電子がその光子を吸収して励起状態へと遷移すると考えるのが厳密である。
2 光と分子の関わりを探る
分子の励起状態
前節で、分子中の電子が励起状態にあると、光を放出して基底状態に遷移することができることを述べた。励起状態にある電子を持つ分子は、電子励起状態にある。同様に、基底状態にある電子を持つ分子は、電子基底状態にある。分子には電子励起状態の他に、2種類の異なる励起状態がある。振動励起状態では、電子は基底状態にいるが、電子の容器である分子骨格が揺れて振動している。回転励起状態では、電子は基底状態にいて、分子振動も励起されていないが、分子が全体として回転している(図5)。分子振動や分子回転の運動が起こると、電子自身が基底状態にあっても容器の振動や回転と一緒に動くために、光から見ると電子がある振動数で振動しているように見える。その結果、分子振動や分子回転も電子自身の運動と同様に光と共鳴相互作用することができる。そのときの共鳴振動数、すなわち光が感じる振動数は、分子振動や分子回転の振動数に他ならない。電子励起状態と電子基底状態の間の遷移を電子遷移、振動励起状態と振動基底状態の間の遷移を振動遷移、回転励起状態と回転基底状態の間の遷移を回転遷移と呼ぶ(図5)。振動遷移と回転遷移が同時に起こる遷移を振動・回転遷移、電子遷移と振動・回転遷移が同時に起こる遷移を電子・振動・回転遷移という。また分子に光を吸収させて励起状態(電子励起状態、振動励起状態、回転励起状態のどれでも良い。以下同様)に遷移させることを、分子を光励起するという。
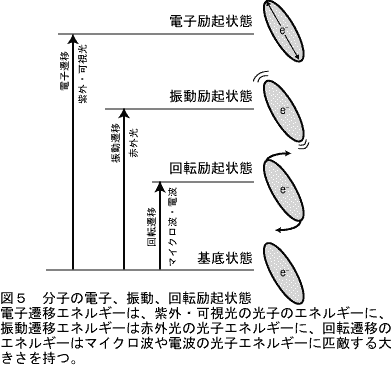
図5
光と分子の相互作用
光と分子の相互作用は光の吸収、光の放出、光の散乱の3つの基本形に整理することができる。光の吸収では基底状態にあった分子が光子を吸収して励起状態に遷移する。後で述べるように、光合成はクロロフィル分子が可視光を吸収して電子励起状態に遷移することによりスタートするし、視覚は網膜上にあるロドプシンという蛋白質中のレチナール色素が、可視光を吸収して電子励起状態に遷移することから始まる。また、電子レンジ中の食品が加熱されるのは、食品中の水分子がマイクロ波を吸収して回転励起状態に遷移し、そのエネルギーを熱として放出するからである。このように、光の吸収は我々の身近なところでさまざまな役割を果たしている。
光の放出は、発光とも呼ばれ、励起状態の分子が光子を放出して基底状態に遷移する過程である。発光がおこるためには、分子が何らかの形でエネルギーを与えられて、励起状態になっていなければならない。キラキラ輝くダイヤモンドは、自身で発光しているのではなく、単にまわりの光を多くの異なる方向に反射しているに過ぎない。したがって、完全な暗闇ではダイヤモンドは光らない。目覚まし時計の夜光塗料はどうだろうか。夜光塗料も完全な暗闇の中では光らない。どこからもエネルギーを与えられていないからである。夜光塗料が光るためには、わずかではあるが光が存在し、その光を吸収して励起状態に遷移できることが必要である。蛍は完全な暗闇でも光る。これは特殊な化学反応により、ルシフェリンという分子の励起状態が蛍の体内で合成されるからである。
光の散乱は、1個の光子が吸収されるとともに、1個の別種の光子が放出される過程である。このとき、分子は基底状態に止まっていることもできるし、また励起状態に遷移することもできる。分子が基底状態に止まったまま起こす散乱をレイリー散乱と呼ぶ。一方、分子が励起状態に遷移しながら起こす散乱を、発見者であるインドの物理学者C.V.Ramanの名に因んでラマン散乱と呼ぶ。晴天時の空が青く見え、夕日が赤く見えるのは、地球の大気中にある分子により太陽光がレイリー散乱されるからである。分子がレイリー散乱を起こす確率は、光の波長が短いほど大きくなる。したがって、波長の短い青色の光は、波長の長い赤色の光よりも大きな確率で散乱される。晴天時に空を見上げたとき我々の目に入るのは、大気中の分子によってレイリー散乱された光であり、その散乱光の中では青の成分が赤の成分より強い。そのため空が青く見えるのである。一方、夕日を見る時には、大気を通過してきた太陽光そのものが目に入る。大気を通過する過程で青色の光は赤色の光よりもレイリー散乱されやすいので、目に到達する光には赤の成分のほうが青の成分より多く含まれる。したがって夕日は赤く見えるのである。
分子のスペクトルと分子分光学
分子のスペクトルは、関与する遷移の種類によって電子スペクトル、振動スペクトル、回転スペクトルの3種類に分類される。一方、光と分子の相互作用の種類によって、吸収スペクトル、発光スペクトル、ラマン散乱スペクトル(以下ラマンスペクトルと略す)の3種類に分類されることもある。これらの2通りの分類は、スペクトルを分子の側から見るか光の側から見るかによる違いによるもので、前者はスペクトルにより与えられる分子情報の種類に、後者はスペクトルが得られる手法に対応している(表1)。
表1
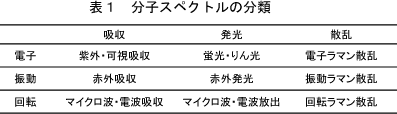
吸収スペクトルはさらに、現れる波長領域によって、紫外・可視吸収スペクトル、赤外吸収スペクトル、マイクロ波・電波吸収スペクトルに細かく分けられる。小数の例外を除き、紫外・可視吸収スペクトルは電子スペクトル、赤外吸収スペクトルは振動スペクトル、マイクロ波・電波吸収スペクトルは回転スペクトルを与える。これは、電子遷移の振動数が紫外・可視領域の光の振動数と、振動遷移の振動数が赤外領域の光の振動数と、回転遷移の振動数がマイクロ波領域の光の振動数と対応するからである。振動数とエネルギーはプランク定数により結び付けられているから、遷移エネルギーと吸収または放出される光子エネルギーの間にも同様の対応がある(図5)。
発光スペクトルとして重要なのは、紫外・可視領域に現れる蛍光・りん光スペクトルである。赤外領域やマイクロ波・電波領域での発光スペクトルは、特殊な実験条件のもとでしか観測されない。ラマンスペクトルは、紫外・可視・近赤外領域のレーザー光を励起光源に用いて観測される。ラマンスペクトルは、赤外吸収スペクトルと同様に、主として振動スペクトルを与える。
電子スペクトルの例として、図6にメタノール中のチアシアニン色素類の紫外・可視吸収スペクトルを示す。横軸に波長(nm単位)、縦軸に吸光度と呼ばれる吸収の強度を表す無次元の量をとってある。チアシアニン色素類は、その中央部にメチン鎖とよばれる ( C=C-C ) nで表される共役電子系を持っていて、その鎖長に応じて異なる吸収スペクトルを持つ。n=0の時には約400nmの光を吸収する。その結果、n=0のチアシアニン色素のアルコール溶液を透かしてみると黄色に見える。これは白色光の成分のうち紫、藍、青の光が吸収され残った緑、黄、橙、赤が目に到達し、その混合色として黄色が見えるからである(緑と赤を混ぜると黄色になる)。一方、n=2のチアシアニンは約620nmの光を吸収し、そのアルコール溶液は美しい青色を示す。これは赤、橙、黄、緑が吸収され、青、藍、紫が残るからである。このようなチアシアニン色素の吸収スペクトルの特徴は、メチン鎖の長さ(電子の容器である分子の長さ)によって電子の励起状態の振動数が系統的に変化することに由来する。すなわち、電子が動ける空間が大きいほど励起状態の振動数が小さくなり、その結果共鳴振動数も小さくなり、吸収する光の波長が長くなるのである。先に分子は光のアンテナであると述べたが、アンテナの長さが長くなるほど、そこに出入りする光(=電磁波)の波長は長くなるのである。このように、紫外・可視吸収スペクトルは電子の運動状態についての情報を与える。なお、チアシアニン色素類は、カラー写真の増感色素(特定の波長を選択的に吸収して感光させる色素)として用いられている。
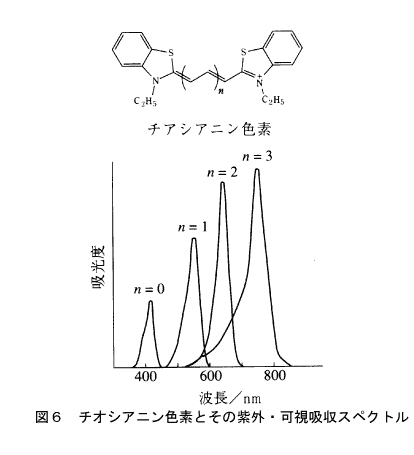
図6
次に振動スペクトルの例として、図7(a)にヘキサン溶液中のレチナールの3種の幾何異性体、全トランス体、13-シス体、9-シス体の赤外吸収スペクトルを示す。ここでは横軸は波数(cm-1単位)、縦軸は吸光度を表している。赤外吸収スペクトルやラマンスペクトルから得られる振動スペクトルは、「分子の指紋」と言われ、分子の構造を鋭敏に反映する特性を持っている。図7(a)からわかるように、赤外吸収スペクトルで見るとレチナールの3種の幾何異性体を明瞭に区別することができる。一方、図7(b)に示す紫外・可視吸収スペクトルは、互いによく似ており区別がつかない。この例からわかるように、振動スペクトルは電子スペクトルに比べて格段に豊富な分子構造情報を含んでいる。
回転スペクトルについては、すでにI章で述べられている。
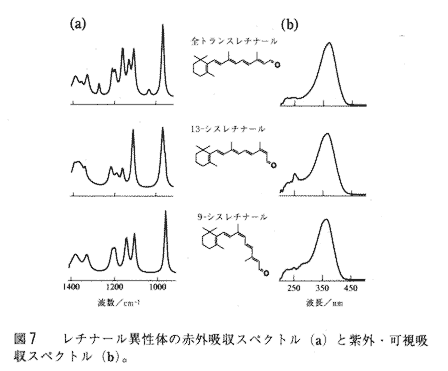
図7
時間分解分光法
暗闇でストロボをたいた写真を撮ると、ストロボが光った瞬間のスナップ写真が得られる。同様の原理を分子分光学に応用したのが時間分解分光法である。時間分解分光法を用いると、分子のスナップ写真に相当する時間分解スペクトルが得られる。ただし、人間のスナップ写真を撮るには1/1000秒(ミリ秒)のシャッタースピードがあれば十分であるが、分子が変化していく様子を観測しようとすると、ナノ(10-9)、ピコ(10-12)、フェムト(10-15)秒の超高速ストロボが必要となる。近年のレーザー技術の進歩により、このような極短時間しか光らないレーザーが開発され、極めて短い時間間隔のレーザー光パルスが利用できるようになった。
図8は時間分解分光法の一つである、ポンプ=プローブ時間分解ラマン分光法の原理を示すブロック図である。この方法では、2つのレーザー光パルス、ポンプパルスとプローブパルスを組み合わせて使用する。ポンプパルスの波長は観測対象とする分子の吸収波長に合わせておく。ポンプパルスをまず試料に照射し、分子を文字どおり基底電子状態から励起電子状態にくみ上げる。つぎに一定の時間間隔(これを遅延時間という)を置いてプローブパルスを試料に照射し、試料から出てくるラマン散乱を観測する。プローブパルスは、ポンプパルスにより励起状態に遷移した後の分子を撮影するためのストロボの役割を果たすわけである。遅延時間を変えてゆくと、分子が時々刻々と変化していく様子を、ラマンスペクトルを通じて手にとるように観測することができる。
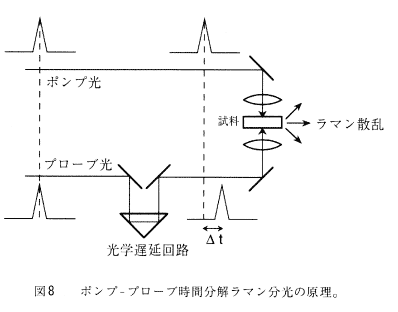
図8
3 光物理化学の最前線
光合成のしくみ −光電子移動反応
光を吸収して励起状態に遷移した電子は、勢い余って分子から飛び出してしまうことがある。これが光電子移動反応である。図9はエタノール中のビフェニルを光で励起した後の時間分解ラマンスペクトルである。横軸は励起光の波数と散乱光の波数の差(これをラマンシフトといい、cm-1単位で表す)で、縦軸はラマン散乱強度である。図9を見ると、光励起とともに電子励起状態のピーク(三角▲印)が立ち上がり、30ナノ秒後には消滅する。カチオンラジカル注)のピーク(四角■印)が励起後やや遅れて立ち上がり、ゆっくりと消滅する。一方、アニオンラジカル注)のピーク(丸●印)はカチオンラジカルのピークより遅れて立ち上がり、かつ早く消滅する。光励起後のビフェニルのこのような挙動は、次のように説明される。ビフェニルは光を吸収してまずは励起電子状態に遷移する。励起電子状態では電子が活発に運動しているので、ある特定の条件が満たされると、電荷がビフェニルからエタノールの中へ飛び出す。その結果カチオンラジカルが生成する。溶媒中に飛び出した電子は、溶媒中を移動し、光で励起されていない基底電子状態のビフェニル分子と出会うと、それと結合してアニオンラジカルを生成する。したがって、光励起後、電子励起状態、カチオンラジカル、アニオンラジカルの順に生成することになる。またアニオンラジカルが先に消滅することは、上記の過程を逆に辿り、まずアニオンラジカルが電子を放出し、次にその電子とカチオンラジカルが再結合すると考えれば、うまく説明がつく。この例で示されたように、光によって生成した励起状態の電子は、隙あらば分子から飛び出そうと機会をうかがっているのである。どのような環境のもとで電子が飛び出しやすく、またどのような環境の下で飛び出しにくいかを解明することは、現代光物理化学の大きな課題の一つになっている。これが解明されれば、光電子移動反応の制御、ひいては太陽光エネルギーの有効利用や光情報処理など次世代の科学技術に直接つながっていくと考えられているからである。
注) ペアになっていない不対電子を持つ分子種をラジカルと総称する。中性の分子から電子が1個とれると、正の電荷を持つカチオンラジカルが生成し、中性の分子に電子が1個付加すると負の電荷を持ったアニオンラジカルが生成する。
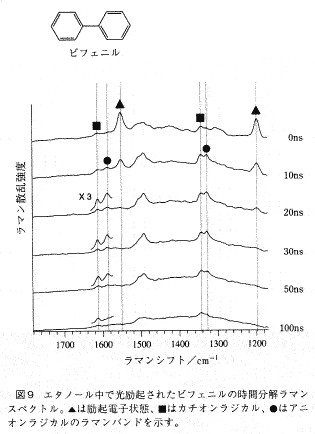
図9
実は自然は極めて巧妙な方法で光電子移動反応の制御を行っている。図10は、光合成を行う細菌(光合成細菌という)の一種から取り出した光反応中心と呼ばれる色素-蛋白質複合体の模式図である。この複合体は、バクテリオクロロフィル(BC)、バクテリオフェオフィチン(BP)、メナキノン(MQ)などの有機分子が、空間的に一定の規則を持って配列したミクロな3次元分子構造体である。光電子移動反応は、一対のBC分子からなるスペシャルペアSPから図の右下のBC分子に向かっておこり、つぎにBCからBP,BPからMQというように一定のシークエンスにしたがって進行する。このような光電子移動のシークエンスは、種々の時間分解分光による研究によりごく最近になって明らかになったもので、光物理化学研究の大きな成果の一つに数えられている。図10のような空間配列が、何故上記のような光電子移動のシークエンスを作り出すのか、その理由はまだわかっていない。とくに、1)光電子移動の出発点であるスペシャルペアが、何故一対のBC分子からなる構造をしているのか、2) 対称に構築されているように見える右側と左側の経路のうち、何故右側の経路のみが選択されるのか、の2つの大きな謎が残っている。今後の研究による解明が待たれる。
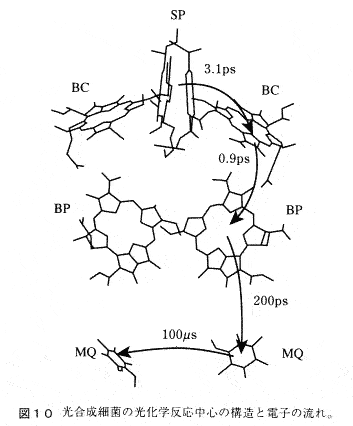
図10
目は何故見える −光異性化反応
光を吸収して電子が励起されると、分子の中の化学結合の性質が変化し、基底状態では起き得ない二重結合のまわりの回転や、結合の組み替えが起こる。これが光異性化反応である。図7に示した全トランスレチナールをヘキサン中で光励起すると、13-シスおよび9-シス異性体が生成する。一方、全トランスレチナールをアルコール中で光励起すると、13-シスおよび9-シス体だけでなく、11-シス体や7-シス体も生成することがわかっている。どのような条件のもとで、どのような経路を通って、どの異性体が生成するのだろうか?この謎がとければ、レチナールの光異性化反応の経路を外部からコントロールする道が開ける。そうすると、図11のようなレチナール光分子ロータリースイッチが実現するかもしれない。
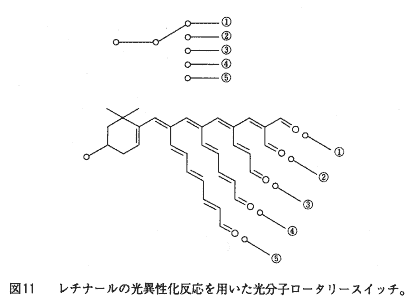
図11
ここでまた光物理化学の最前線が生物学とオーバーラップする。実は自然界ではレチナール分子スイッチが既に実現されているのである。動物の視覚は、網膜上に存在するロドプシンと呼ばれる膜蛋白質によって起動される。ロドプシンの中にはアミノ酸残基と結合した11-シスレチナールが含まれていて、光を吸収すると全トランス体へ異性化する。この光異性化反応によりレチナール分子の構造が大きく変化するので、周りを取り囲む蛋白質の構造に歪みが生じる。この蛋白質構造の歪みが以後のプロセスの引き金となるのである(図12)。また、バクテリオロドプシンと呼ばれる膜蛋白質は、光を吸収してプロトンを膜の内側から外側へ運搬するプロトンポンプの働きをするが、この膜蛋白質は全トランス-レチナールを含んでいて、それが13-シス体へ光異性化することにより、反応のサイクルが開始される。これらの光生物過程では、溶液の光異性化反応とは異なり、光の吸収後特定の異性体のみが選択的に生成する。ロドプシンやバクテリオロドプシンは、おそらく蛋白質部分のアミノ酸残基の3次元空間配置を最適化することによって、レチナール部分の環境を、特定の光異性化反応の経路のみが選択されるように巧妙に制御しているのであろう。現在、様々な時間分解分光の手法を用いて視覚やプロトンポンプの機構を解明する研究が行われている。これらの研究は、単に光生物学現象の解明にとどまらず、光異性化反応、さらには化学反応一般を制御する方法の開発につながってゆくものと期待される。
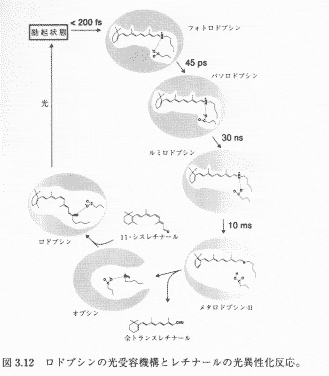
図12
光コンピュータの夢
今後加速度的に進行するであろう情報化時代に向け、分子を用いた超高速光演算素子や超高密度光メモリーを開発するための基礎研究が、現在盛んに行われている。このような研究の成否は、光と分子の関わりを我々がどこまで深く理解できるかの一点にかかっている。すなわち、光励起された分子が、どのような経路を経て、どのような時間スケールで、どのように変化していくか、それを決める一般原理の確立を求められているのである。ひとたびこの原理が確立されれば、要求される光応答特性、光演算素子であれば光に対する超高速応答、光メモリーであれば光誘起変化の継続性や可逆性など、を持つ分子や分子集団の設計、構築が可能となる。
スピロオキザジンとよばれる分子1は無色であるが、これに紫外光をあてると、1ピコ秒以内に中央部の6員環のC-O結合が開裂し、青色の分子メロシアニン2が生成する。このように、光をあてると物質の色が変化する現象をフォトクロミズムという。
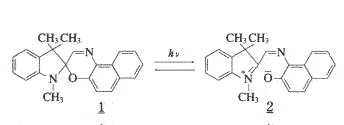
図13
2の寿命は温度や環境に強く依存する。2は低温ガラス注)溶媒中では長時間安定に存在するが、常温溶液中では極めて速く1にもどってしまう。また赤色の光をあてると、低温ガラス中でも1にもどる。
注) 液体のように透明であるが、流動性のない固体をガラスと総称する。
このようなフォトクロミズムを示す分子を光メモリーとして用いる可能性が検討されている。すなわち、紫外光を書き込み光、赤色光を読み出し光に用いれば、書き込みされているか否かを、赤色光の吸収の有無によって知ることができる。しかし、1を用いて実際に光メモリーを作ろうとすると多くの障害がある。例えば、書き込まれた情報を保持するには、2の寿命が十分に長くなければならない。また、読み出し光の赤色光により、2から1への逆変換が起こると、読み出しを行える回数に制限が生じることになる。これらの難点を解消するためには、2の寿命を決めている環境要因が一体何であるのか、また赤色光による2から1への逆変換はどのような機構で起こるのかという光物理化学の基本問題を解明することが必要になる。
光合成を代表とする光エネルギー変換、視覚を代表とする光情報処理、また夢の光コンピュータなど、光の世紀とよばれているこの世紀の主要科学技術は、すべて光と分子の関わりを探る光物理化学的基礎研究をその土台としているのである。